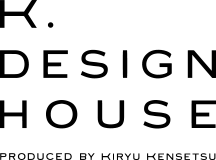注文住宅で実現する終の住処の理想形

注文住宅による終の住処の理想形を考えてみます。人生にはさまざまな転機があります。結婚や子どもの巣立ち、定年を迎える頃などがそうでしょう。
人によっては様々なライフステージの変化があると思います。そして、誰でも共通しているのは、確実に歳をとっていくことです。
まだまだと思いながらどこかで人生の終わりを意識することもあるでしょう。「終の住処」という言葉がありますが、その言葉を意識するのはいつ頃でしょうか。
注文住宅で家づくりをする大半の方は、終の住処となることを意識していることでしょう。それだけに、納得のいく家づくりをしたいものです。
目次
快適空間の設計

家づくりで一番に意識したいのは快適空間ではないでしょうか。さまざまな快適設備や機能がありますが、それらはすべて住みやすさに直結します。
多機能で至れり尽くせりだから住みやすいのか、反対にシンプルで何もないけど住みやすいと思うこともあるでしょう。
人の数だけ違った価値観があるので、まずは自分のライフスタイルを下敷きにして家づくりの基本を考えるようにします。
押さえるべきところは押さえながら、すべてを追い求めるのではなく、パーソナライズされた快適空間を目指すように家づくりを考えましょう。
ライフスタイルに合わせたカスタムデザイン
家づくりの際に基本としたいのは自身のライフスタイルや家族構成を考慮したカスタムデザインです。そして、なによりも暮らしやすさを重視しなくてはいけません。
完成した後に、「どうしてこんな間取りにしたんだろう…」というようなことがないようにしたいところです。そのためにも、夫婦2人でスタートする場合、将来の家族構成を思い描きながら、柔軟性に富んだ家づくりを基本としましょう。まずは日常生活を快適にする暮らしやすさを第一に考えます。
多目的スペースの活用法
リビングのほかにもうひとつ多目的スペースがあれば便利です。特に夫婦2人でのスタートではさまざまな使い道が考えられます。
ゲストルーム
勉強部屋
遊び部屋
書斎
同居対応
多目的スペースがあると、家族構成の変化にも柔軟に対応が可能です。
将来的にどのような部屋にも対応可能な多目的スペースは無駄になりません。
個性を反映したインテリア
カスタムデザインは家づくりだけではありません。おしゃれなインテリアによって見た目の雰囲気が変わってきます。
落ち着いたアンティークに凝ってもよいですし、春のような明るさを追い求めてもよいでしょう。
最初に考えたインテリアデザインは時を経ると代えがたいものがあります。そのインテリアデザインを替えるときが人生の転換点でもあり、それはそれでターニングポイントとして記憶に残るものとなります。
それだけ、個性を反映したインテリアにこだわってみたいものです。
バリアフリー設計

20代あるいは30代で考える家づくりには、将来に思いを馳せた住宅設計にはならないかもしれません。自分自身がしっかり動けますし、親もまだまだ元気な世代です。
一方で40歳以降となると、自身の健康面での不安を感じる頃で、それを家づくりにも反映するべきでしょう。
その考えを実現するのがバリアフリーです。元々は建築用語で物理的な障壁の除去の意味で使われてきました。
それが現在では、高齢者や障害のある方に限らずすべての人に対してハード・ソフト両面の障壁の除去の意味で用いられています。
家族みんなに優しい設計
バリアフリーは高齢者向けあるいは障害のある方向けといったイメージが定着しています。間違いではありませんが、段差のない住宅はとても住みやすいものです。
妊婦や子どもさんにも優しいですし、何よりも安全に留意しているところがその家に住んでいる人全員の安心感につながります。
最初の家づくりでは、すべてをバリアフリーにする必要はないかもしれませんが、将来のリフォームに向けた取り組みを家づくりの際にしておいてもよいでしょう。
アクセシビリティという言葉もよく聞くようになりました。Access(近づく)とAbility(能力)を合わせた言葉で、家づくりのアクセシビリティは誰もが情報や機能を利用できることです。
そのため、単に段差をなくす、転倒を予防するだけに限らず、使いやすさを考慮したさまざまなアクセシビリティの強化が必要です。
全世代に対応する設計
バリアフリーやアクセシビリティを超越した、すべての人が利用しやすい考え方を実践するのがユニバーサルデザインです。
バリアフリーは主にハード的なものとなりますが、それにソフト(精神的)なものを取り入れたものがユニバーサルデザインと考えてよいでしょう。
将来的にも暮らしやすい家づくりとなると、バリアフリーは避けて通れないものとなります。高齢者向けあるいは障害のある方の方向けだけではなく、そこに住む全ての方のための住宅設計と考えれば自ずと答えが出るものかもしれません。
環境に配慮した家づくり

環境に配慮した家づくりであれば、まずは素材を考えたいところです。現在家づくりで、建材の主流となっているのはプラスチックです。
意外に思われるかもしれませんが、木材のように見えて素材はプラスチックというケースも少なくありません。
プラスチック素材が使われているのは第一に安価であること、軽くて丈夫であることも見逃せません。そしてデザインに自由度があるので理想の家づくりに欠かせない素材です。
一方で、環境面で考えると天然の木材がよいのは間違いありません。コストなどあらゆる面を考慮しながら適材適所で素材を使い分ける柔軟さを持って家づくりを考えたいところです。
環境に優しい建材の選び方
建材はプラスチックで、といった家づくりも少なくありません。安価であることはもちろん、抗菌や消臭にも優れています。
建材はすべてプラスチックというわけではありませんが、床材などあらゆるところでプラスチックが使われています。
一方で環境への配慮から脱プラスチック化も進んでいます。プラスチックを用いるのではなく、プラスチック建材を作る過程ですでに環境破壊を起こしている考え方です。
そのため、環境に優しく、再生可能資源としてリサイクルにも活用できる天然無垢材が注目されています。
デメリットとしてはプラスチック建材に比べて高価なところと、木材全般にいえますが水や湿気に弱いところです。
現在はそういった弱点を克服したコルクタイルが注目を集めています。
コルク材を圧縮した加工材ですが、コルク樫の皮を使用するので伐採することなく、水にも強く軽くて丈夫で安価な点でキッチンやトイレ、洗面所などの水回りでの使用に特に適した素材です。
エネルギー効率を高める設計
エネルギー効率を高める家づくりを考えてみましょう。例えば、断熱技術の導入による省エネの実現です。
それによって、冷暖房費を抑えることができ、結果的に環境に配慮したことになります。
そのためには、高品質な断熱材の使用が必要ですが、断熱による省エネ効果である期間で損益分岐点を超えてお得になるのは間違いありません。
同様に太陽光発電とオール電化を組み合わせることで、太陽光を電気に変える分だけ省エネになります。
自然と共生する住まいのデザイン
「バイオフィリア効果」という言葉があります。これは、天然素材を取り入れることで自然とふれあいながらストレスを軽減するものです。※フィリアは愛着という意味です。
家づくりに取り入れるなら、自然と共生する住まいということになります。簡単なところでは観葉植物を取り入れるなどがあります。
趣味が高じて室内がジャングルのようになるケースも少なくありません。観葉植物に限らなくても天然木材の使用で自然との共生が可能です。
森林伐採につながる批判もありますが、伐採と植樹のサイクルをしっかり確立させることが大切で、国内ではそういったシステムがすでに構築されています。
省エネ設備とスマートホーム技術

スマート照明でエネルギー効率アップ
照明はすでにLEDに変わっており、現在はスマート照明の時代に入っています。
ここ数年のトレンドといってもよく、かけ声一つあるいは手を叩くだけで照明のオンオフが可能です。
照明の加減も自由自在に変更が可能です。こういったスマート照明に人感センサーやタイマー機能を活用した照明制御システムが現在の姿といってもよいでしょう。
スマートサーモスタットで快適温度管理
これからのスマートホーム技術として注目されているのがスマートサーモスタットです。2020年を1として2027年度までに1.28倍になると予想されています。
スマートサーモスタットは、自動温度設定を可能にする電子機器のことです。あらゆる天候に対応した冷暖房のニーズ、さらには日々のスケジュールなどによってプログラム可能な温度管理を実現します。
AI技術も取り入れられており、周囲の環境のパターンを学習して冷暖房システムの適切なエネルギー効率を実現します。
機器としてはすでに完成されたもので、スマートサーモスタットを活用したシステムの構築も進んでいます。
インターネットを介してスマホやタブレットなどのデバイスからアクセスが可能で、スマートホームの中核となるシステムとなるでしょう。
スマートプラグとエネルギーモニタリング
スマートプラグはそれ自体にWi-Fi機能を内蔵したコンセントのことで、スマートコンセントとも呼ばれています。火災の危険性があるなど利用できない家電もありますが、スマートプラグを介して家電を接続するだけでスマートデバイスとして機能させることができます。
普通の家電製品をネットを介して操作が可能なので、一抹の不安を感じる方も少なくないでしょう。スマートプラグの多くにエネルギー監視機能が内蔵されているのでエネルギーのモニタリングが可能となっています。
そのため、誤操作による電気の使いすぎを防ぎ、反対に節電効果を高めます。
未来への投資を考えた住宅設計のコツ

家づくりを住宅投資と考えたら、家づくりに対する考え方も変わってくるかもしれません。終の住処にするのだから投資とは考えていない、という方もいると思います。
いっぽうで住宅は財産ですから、そこにお金をつぎ込むことは立派な住宅投資です。
終の住処を意識した家づくりをしても、将来のことは予想通りにいくとは限りません。引っ越さなければいけないこともあるでしょう。
そういった不測の事態にリセールバリューがあれば、お金の問題が少しは楽になります。そういったことも考えた住宅設計のコツをご紹介します。
持続可能な素材の選定とエネルギー効率の向上
家づくりは投資と考えて間違いありません。それは住宅がおそらくどの家庭でも一番の財産になるからです。
建物自体は20年でその価値がゼロになると言われていますが、それは不動産業界に限ったものです。20年を経過しても必要な人にとっては数百数千万円の価値になることでしょう。
土地にいたっては、購入時よりも地価が上がっているかもしれません。
家づくりの際に将来的なリセールが念頭にあるのであれば、安価な素材を使った節約志向にならないと思います。
環境に優しい建材と省エネ技術を取り入れた住宅設計でリセールバリューが高まります。
資産価値を最大化するデザイン戦略
素材やエネルギー効率に目を向けて、さらに資産価値を増大させるのがデザインです。家づくりに重きを置いて自らデザインを行うオーナーもいれば、既存の住宅で満足するオーナーもいます。
家づくりをする人、家さがしをする人に分かれるのです。
家さがしをしている人に対して訴求効果を高め、長期的な視点で将来のリセールバリューを考えた魅力的な家づくりが望まれます。
未来を見据えた投資
日本の住宅は耐用年数が短いのがネックとされてきました。そのため10年20年おきにリフォームが必要であり、住宅ローンと平行してリフォームの費用を捻出しなくてはならず、かなりの家計負担となることは否めません。
家のメンテナンスをしっかり行うことは、住みやすさを継続する意味でもおろそかにできませんし、リセールを考えているのであれば同様にしっかり行う必要があります。
終の住処を思っての家づくりであっても、将来的に引っ越さざるを得ない場合もあります。そういった事態を想定しながら、リフォームメンテナンスを頭にいれた家づくりが大切です。
調和を考えた立地選び

家づくりでは立地も大切です。というよりも立地ありきで家づくりがあると考えてよいでしょう。まずは場所を決めてそこに家を建てるイメージです。
誰でも交通の便がよくてある程度都会で職場や学校に近いといった恵まれた土地の取得を目指したいでしょう。
いっぽうで車があれば校外でも問題ないと思う方も少なくありません。
土地探しにはそれだけではなく、将来的に立ち退きの心配のないような土地選びにしたいものです。ここでは立地について紹介します。
地域社会との共生を重視した立地選び
都会では地域とのつながりが希薄になったといわれて久しいですが、地方では町内会は力があり、町内会費の徴収から町内でさまざまな活動が行われています。
地域社会はそこに住んでみないとわからないところが多く、逃げ場がないだけに地域に馴染めなければ少々難しい問題も起こりかねません。
そのために、できるだけ家づくりあるいはその前の立地選びの段階で、その地域の町内会の活動や隣近所の雰囲気などを、探ってみるのもよいでしょう。
難しいとは思いますが、不動産会社からの情報や近隣に住む知り合いなどがいれば、貴重な情報が入手できるかもしれません。
公共施設やサービスへのアクセスの良さ
住みやすさは住宅だけではありません。その地域の公共施設の充実やサービスなども家づくりには大切な要素です。
近くに公民館があれば、さまざまな講座や催しがあり、興味のあるものには安価で参加が可能です。
また、その地域ならではの行政サービスを受けることができればさらにお得度が増すでしょう。
駅や病院やスーパー、学校などが近くにあれば、生活するには十分すぎる環境です。
環境との調和を考えた自然豊かな場所の選定
戸建て住宅のメリットはあらゆる場所を選べることです。反対に駅近や市内中心部など利便性を追求するのであればマンションのほうがメリットが大きいでしょう。
自然豊かな場所の選定は家づくりの際の醍醐味ですし、立地によって家のデザインのイマジネーションも沸き立ちます。
気をつけたいのは、入念な下調べをして土地の購入を考えることです。将来的に土地の再開発が起こりそうな場所は敬遠しなくてはいけません。
その点では不動産会社が十分な情報を持っているはずなので事前のリサーチは入念に行いましょう。
まとめ
年代によって住宅に対する考え方も変わってくるでしょう。
どの年代でも共通しているのは、自身の希望する暮らし方を追い求めるということです。立地は便利なところがよいと紹介しましたが、介護サービスの利用もできるので、それほどナーバスになる必要はありません。
終の住処でどのような暮らし方をしたいのかにも思いを巡らせた家づくりを考えたいものです。